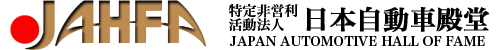日本自動車殿堂イヤー賞選考要領

日本自動車殿堂 イヤー賞選考委員会委員長
廣瀬 敏也
1.日本自動車殿堂イヤー賞の種類
当該年度の最も優れた乗用車およびその開発チームを表彰する。
(1)日本自動車殿堂カーオブザイヤー
(国産乗用車)
(2)日本自動車殿堂インポートカーオブザイヤー
(輸入乗用車)
(3)日本自動車殿堂カーデザインオブザイヤー
(国産乗用車)
(4)日本自動車殿堂カーテクノロジーオブザイヤー
(国産乗用車)
* (1)、(3)、(4)は国産乗用車から選考する。輸入乗用車はデザイン、テクノロジーも含めて総合的に(2)で選考する。
2.年次の選考対象期間および選考対象車
2022年10月16日から2023年10月15日を選考対象期間とし、同期間に発売された新型車を選考対象車とする。
3.選考委員会
大学で自動車に関わる研究をしている研究者・教員の方や、自動車メーカーなどで開発・実験、デザインなどの業務に従事したのち、大学などの教員として教鞭をとっている方などに選考委員を委嘱し、選考委員会を組織する。
日本自動車殿堂では、日本自動車殿堂カーオブザイヤー、同インポートカーオブザイヤー、同カーデザインオブザイヤー、同カーテクノロジーオブザイヤーそれぞれ4賞について選考委員を委嘱する。各賞選考委員の重複(兼任)は妨げない。
4.選考委員会事務局の設置
選考委員会にはノミネート車の選定、選考委員への連絡・情報提供、投開票などの実務を担う選考委員会事務局を組織する。
5.選考の主眼
自動車は「国民の日々の生活と移動を支える重要な手段である」との観点から、各選考委員の知見を活かしつつ、一般市民の感覚を重視し、乗る、使う、買う人たちの視点にも立った評価を行なう。
また自動車は高級セダンからスポーツカー、大衆車、軽自動車まで、カテゴリーやジャンルがあり、技術も価格も千差万別となっている。さらには技術面でも電動化や自動運転の進展など、自動車も大きく変わりつつある。そうした多様な車を一律に評価するだけでなく、それぞれのジャンルの中で優れている車や、先進性を感じさせる車、という視点を持ち、選考を行なう。
以上のように、日本自動車殿堂イヤー賞の各賞は、コンセプト、技術、スタイル、バリューフォーマネー等に優れた自動車を選ぶことを基本とする。
6.評価項目
4賞それぞれについて、下記のような評価基準を設け、それに準拠しながら総合的に選考を行なう。
(1)日本自動車殿堂カーオブザイヤーおよび日本自動車殿堂インポートカーオブザイヤー
1「デザイン」、2「先進性・独自性」、3「実用性・利便性」、4「経済性」、5「安全性」、6「環境性」、7「買い得感」、8「完成度」
(2)日本自動車殿堂カーデザインオブザイヤー
1「エクステリア」、2「インテリア」、3「カラー」、4「素材」、5「先進性・独自性」、6「調和性」、7「機能美」、8「完成度」
(3)日本自動車殿堂カーテクノロジーオブザイヤー
1「先進性・独自性」、2「実用性・利便性」、3「価格パフォーマンス」、4「信頼性」、5「機構のシンプルさ」、6「環境・安全性」、7「UI(ユーザーインターフェース)」、8「完成度」
7.日本自動車殿堂イヤー賞各賞の選考手順
(1)当該年次の各対象車種の選定
選考委員会事務局は、当該年次の対象車「第1次ノミネート車」を選び、これらのうち10数車を「第2次ノミネート車」として選定し、それぞれの所定の投票用紙を添えて選考委員に送付する。
(2)選考委員による投票
選考委員は各自、「第2次ノミネート車」を参考にして、上位5車を選び出し、1~5位までの順位付けをして所定の投票用紙に記入して投票する。1位および2位に選んだ車について、コメント(選考理由)を付す。
(3)集計方法
選考委員会事務局は、選考委員によって投票された車について、1位=10点、2位=8点、3位=6点、4位=4点、5位=2点と換算して得点化し、結果を集計してノミネート各車の順位を決定する。集計にあたっては、必要に応じて統計処理を行なう。これらの結果にもとづき、選考委員会事務局はイヤー賞各賞を決定するとともに選考理由を付し、委員長に報告する。委員長がこれを公表する。
8.選考委員名簿
イヤー賞選考委員会委員長 理事 廣瀬 敏也
芝浦工業大学 工学部 教授
イヤー賞選考委員会副委員長 坂口 善英
坂口デザイン研究所 主宰
イヤー賞選考委員会主幹 牧田 光弘
日本自動車研究所 シニアエキスパート
イヤー賞選考委員会主幹 梶原 伸治
近畿大学理工学部 准教授
(1)日本自動車殿堂カーオブザイヤー
(2)日本自動車殿堂インポートカーオブザイヤー
選考委員名(順不同)
景山 一郎 (日本大学生産工学部 名誉教授)
間宮 篤 ((株)東京アールアンドデー 元副社長)
野崎 博路 (工学院大学 名誉教授)
浅野 邦明 (自動車安全運転センター 元理論教官)
廣瀬 敏也 (芝浦工業大学工学部 教授)
寺本 健 ((株)KENTWORKS 顧問)
梶原 伸治 (近畿大学理工学部 准教授)
東 大輔 (久留米工業大学 専攻長・教授)
吉野 貴彦 (久留米工業大学工学部 准教授)
芝端 康二 (神奈川工科大学 特別客員教授)
金子 哲也 (大阪産業大学工学部 教授)
牧田 光弘 (日本自動車研究所 シニアエキスパート)
坂口 善英 (坂口デザイン研究所 主宰)
杉山 泰成 (日本自動車博物館 顧問)
松本 洋一 (松本技術士事務所 代表)
山本 洋介 (デザイン&リアライゼーションズ 顧問)
木村 徹 ((有)木村デザイン研究所 CDO)
貴島 孝雄 (山口東京理科大学 名誉教授)
清水 康夫 (東京電機大学大学院 教授)
( 3 )日本自動車殿堂カーデザインオブザイヤー
選考委員名(順不同)
石井 明 (九州大学大学院 名誉教授)
河岡 徳彦 (静岡文化芸術大学デザイン学部 元教授)
松井 孝晏 (STUDIO MATSUI 代表)
坂口 善英 (坂口デザイン研究所 主宰)
稲田 真一 (武蔵野美術大学工芸工業デザイン学科 教授)
木村 徹 ((有)木村デザイン研究所 CDO)
東 大輔 (久留米工業大学 専攻長・教授)
片岡 祐司 (名古屋芸術大学 教授)
野崎 博路 (工学院大学 名誉教授)
間宮 篤 ((株)東京アールアンドデー 元副社長)
山本 洋介 (デザイン&リアライゼーションズ 顧問)
廣瀬 敏也 (芝浦工業大学 教授)
牧田 光弘 (日本自動車研究所 シニアエキスパート)
服部 守悦 (静岡文化芸術大学 教授)
貴島 孝雄 山口東京理科大学 名誉教授
高島 晋治 東京都立産業技術大学院大学 教授
佐々木 勝史 (大同大学大学院情報デザイン学科 教授)
( 4 )日本自動車殿堂カーテクノロジーオブザイヤー
選考委員名(順不同)
景山 一郎 (日本大学 名誉教授)
野崎 博路 (工学院大学 名誉教授)
廣瀬 敏也 (芝浦工業大学工学部 教授)
松本 洋一 (松本技術士事務所 代表)
梶原 伸治 (近畿大学理工学部 准教授)
東 大輔 (久留米工業大学 専攻長・教授)
吉野 貴彦 (久留米工業大学工学部 准教授)
芝端 康二 (神奈川工科大学 特別客員教授)
金子 哲也 (大阪産業大学工学部 教授)
牧田 光弘 (日本自動車研究所 シニアエキスパート)
間宮 篤 ((株)東京アールアンドデー 元副社長)
杉山 泰成 (日本自動車博物館 顧問)
石川 和男 ((株)コマツ開発本部)
貴島 孝雄 (山口東京理科大学 名誉教授)
清水 康夫 (東京電機大学大学院 教授)